卵はケーキやパン作りにかかせない基本的な食材の一つですね。ドイツのスーパーや青空市場に行くとたくさん売られています。だいたい6個か10個パックで販売されていますね。
大きさの違いもありますが、パッケージににはBodenhaltungやFreilandhaltungなど記されています。これはどういう意味を持っているのでしょうか?値段の違いもありますし、どこに違いがあるのか気になりますね。
今回は日本とドイツの卵の違い、そしてドイツの卵に関してまとめてみました。
<結論:ドイツの卵事情>
日本とドイツの卵には違いがある。
卵に表記されているスタンプは飼育方法、生産地、生産者を示している
言葉の意味
ドイツ語では卵はEi(アイ)です。複数形の場合はEier(アイアー)となります。
卵にもいろいろな種類がありますが、ドイツのスーパーなどで”Ei”または”Eier”と言う商品名で売られているのは、にわとりの卵だけです。
他の卵、例えば、うずらの卵はWachteleier(バッハテルアイアー)など、”Eier”の前に種類がつきます。魚卵はまた別になりますね。そちらは”Kaviar”(キャビア)と言う言い方になります。
なので、特別”にわとりの卵”と書いていなくても、”Eier”という商品名ならば、にわとりの卵となります。

日本とドイツの卵の大きな違い
日本とドイツで大きく違うのは、洗卵されてから出荷されるかされないかです。日本では基本的に洗卵されて出荷され、冷蔵保存されます。ドイツでは洗卵されずに出荷されるのが基本的です。そのためドイツでは常温で卵が売られています。
卵の周りにある保護膜を残す目的で、ドイツでは洗卵されないそうです。保護膜は細菌が入ってくることを防ぐ効果があります。そのため保護膜の残っているドイツでは常温で、保護膜を洗い流してしまう、日本では冷蔵保存されます。
ドイツの卵は生食に適していないとよく言われます。実際、ドイツでは特に、高齢者、病患者、小さい子供など、抵抗力の弱い人たちは、生食は控えるべきと言われています。ドイツで卵を生で食べるとおなかをこわすという方もいらっしゃいます。もし生食をする場合は、特別新鮮なものを選び、店員さんに尋ねるのもいいと思います。

ぼくたちも生卵が食べたかったので、ドイツの鶏肉屋さんに行って、生で食べれれるか聞いたことあります。店員さんもこれは大丈夫と言ってくれたので、僕たちはそのお店で買っていました。おなかを壊したことはありませんが、注意した方がいいと思います💦
卵の大きさ
ドイツに売られている卵にはS、M、L、XLのサイズで売られています。卵黄、卵白と卵殻、合計の重さで分類され、
- S: 53g以下
- M: 53g~63g
- L: 63g~73g
- XL: 73g以上
となります。スーパーで売られているのはMかLが多いですね。たまにSやXLも見かけますが、珍しいと思います。
僕のレシピで使用しているのは基本的にMサイズです。卵1個50g、卵黄20gと卵白30gで計算しています。
飼育方法による違い
ドイツではにわとりの飼育方法によっても分類されます。
- Ökologische Erzeugung(オーガニック)
飼育小屋の中では、1平方メートルにつき6羽のみの飼育が許されています。全体で3000羽を超えることも許されていません。隣接するエリアには、1羽当たり、最低4平方メートルの屋外スペースが確保されています。飼料の大半はオーガニックのものが使われます。
- Freilandhaltung(屋外飼育)
1平方メートルにつき、9羽まで。畜舎は少なくともBodenhaltungと同じ基準を満たす必要があります。日中、屋外で少なくとも4平方メートルの草地の屋外に放し飼いされます。
- Bodenhaltung(屋内飼育)
基本的には屋内畜舎のみで飼育されます。1平方メートルにつき9羽まで、合計で最大6000羽までと定められています。最大4段まで、にわとりを買う納屋を重ねることができ、その場合は最大1平方メートルにつき、18羽まで飼育することができます。
- Kefighaltung(籠飼育)
小さなケージの中で飼育されています。1平方メートルにつき12.5羽の飼育できます。一つのケージでは最大60羽のにわとりが飼育されています。日本では一般的な飼育方法ですが、ドイツ、そしてヨーロッパでは2025年には完全撤廃する予定で、すでにドイツでもかなり数は少なくなっています。
基本的には上から順に値段が高くなります。

狭い養鶏場のYoutubeを見ると、とても鶏たちがかわいそうだなと感じてしまいます…もしご興味がある方は、一度検索してみてください😢

卵の品質
卵には品質によって、ランクがつけられています。通常買うことができる卵はすべてAクラスです。Bクラスは加工されて販売されることがほとんどですね。
AかBで分けることのできない卵はCに分類され、販売されることはありません。

殻には白と茶色のものが存在しますが、これは品質には関係ありません。にわとりの品種や、遺伝的な要因で変わるようです。
ちなみに卵の黄身は、色が薄いものから濃いものまでさまざまです。これは餌の違いで色が変わります。こちらも卵自体の品質には変わりありません。
卵にスタンプされているコード

ドイツで販売されている卵には、それぞれコードのようなものがスタンプされています。これはこの卵を産んだにわとりがどのように飼育されているか、そしてどこからこの卵が来ているかを示しています。
この例ですと0-DE-0356702となっています。
最初の数字は飼育方法を指しています。0はオーガニックです。1がFreilandhaltung(屋外飼育)、2が屋内飼育、3が籠飼育です。
次のローマ字2文字は、国を指します。DEはドイツです。他の国は例えばNLはオランダ、ATはオーストリアですね。
最後の数字、最初2桁は州を指します。03はNiedersachsenですね。
01 = シュレースヴィヒ=ホルシュタイン
02 = ハンブルグ
03 = ニーダーザクセン
04 = ブレーメン
05 = ノルトライン=ヴェストファーレン
06 = ヘッセン
07 = ラインラント=プファルツ
08 = バーデン=ヴュルテンベルク
09 = バイエルン
10 = ザールラント
11 = ベルリン
12 = ブランデンブルグ
13 = メクレンブルク=フォアポンメルン
14 = ザクセン
15 = ザクセン=アンハルト
16 = テューリンゲン

ヘッセン州で買ったものですが、違うところから来ているのは驚きです。
その次の数字4桁は生産者、および養鶏場にそれぞれ振り当てられている番号です。
ちなみにスタンプに記入されているコードをこのサイトに入力すると、どこから来ているかすぐにわかります。
今回の例、0-DE-0356702ですと:飼育方法はオーガニック、生産地はドイツ、ニーダーザクセン州のアウリッヒ、そして生産者はゲアハード・ハルムスさんということになります。
まとめ
ドイツの卵に関してまとめてみました。
ホテルで働いていたときも、スクランブルエッグ、卵焼き、ポーチドエッグなど、朝食のビュッフェには卵は欠かせませんでした。パティシエとしてもお菓子やパンの材料として欠かせない食材の一つですね。
日本とは違うことも多いですが、ドイツで卵を買うときに参考にしてください。
参考文献



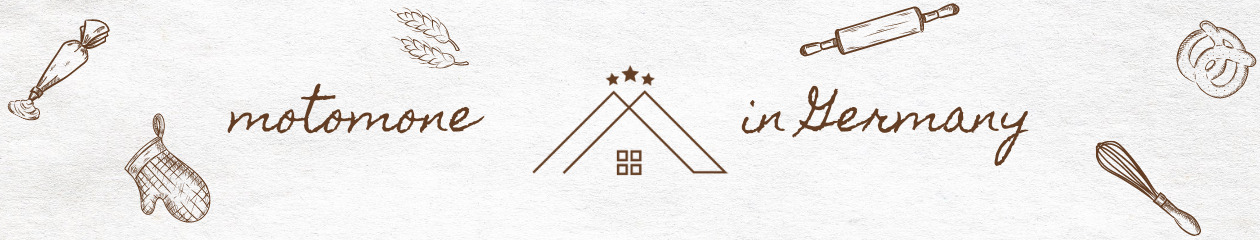
コメント